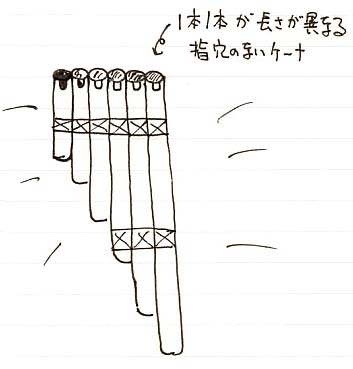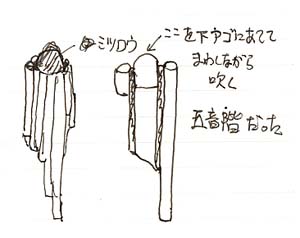サンポーニャ雑学03
2000.12.27.更新
日本に情報が入っていなかった頃の偽のサンポーニャ(?)
ラティーナ誌の全身「中南米音楽」にサンポーニャ・シークと
呼ぶことが多かったが、この作りが載っている。
1976年頃、レコードではウニャラモス、A・パントーハ、ケオパラシオス、
チャコス、ロスインカス、コンフント・マチュピチュ位が、
やっとレコードででていた頃で、第一回のコスキンの始まるくらいの頃。
多分、マチュピチュやチャコスのジャケットの
開管共鳴管を見てそう考えたのだろう。ケーナのような吹き口の笛と。
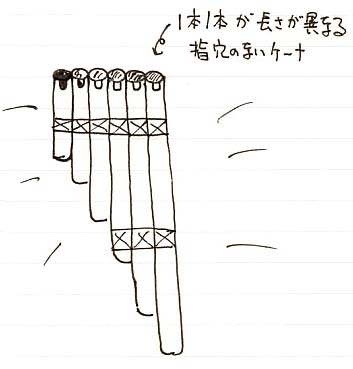 このFolkloreとタンゴの専門紙に作者談として、
このFolkloreとタンゴの専門紙に作者談として、
ウニャラモスのような音がした、と書いてあった。
今でもボリビアの情報は多くはなく、また、正確ではないので、
楽器の分類を書いている今の自分としては笑えないはずなのだが、
当時の未知の事柄に対する情熱は素晴らしい。
専修大OBの作ということであるか、彼は今、この笛の音は出せないという。
(c.f.→ワイラ)
注意 バホン・・・サンポーニャではない。
バホンはサンポーニャのような形をしているかラッパ形の楽器。
世界中にサンポーニャの仲間があるが、タイのものは円筒型のものだった。
5音階のアンタラ。
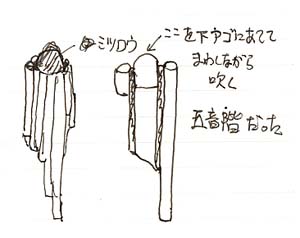 参考 日本 正倉院
吹き口を斜めにカットしてある18管のアンタラ。
参考 日本 正倉院
吹き口を斜めにカットしてある18管のアンタラ。
長さは23.7〜28.8cmの閉館(?)竹を並べ
紙の詰め物で音程を調節する。タブラアンタラ(?!)
12律〜6律。
サンポーニャ雑学04
まうノート・トップ