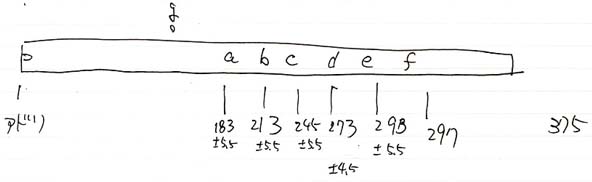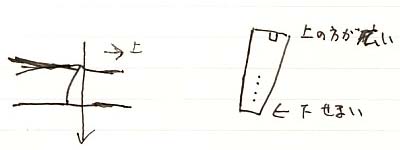04・ケーナの作り方
ケーナの作り方(木村一彦式)
・長さ ボリビア型は約36cm。径によって変化する。
底穴と指穴をふさいだとき、A(ラ・・・少し低めに)倍音をE(ミ)になる長さに調節。
吹き口はきちんと作らないと音程が変わる。浅めにする。
太めの管は短く、細めの管は長くなる。
底に穴をあけて Sol を作る。
1)底穴が大きい・4.5cm← →底穴が小さい・3.5cm
底穴の大きさによって、底部より上3.5〜4.5cmにマークする。・・・マーク1
管の真ん中にマークする。・・・マーク2
2)マーク1とマーク2を5等分と等間隔ぐらいより少し大目の長さでウラ
 Re とFa♯ は、上げすぎないように注意する。
Re とFa♯ は、上げすぎないように注意する。
Sol は低くならないように。
ケーナの吹き口側に角度をつけるのは好ましくない。高音がずれる。
吹き手が、笛の角度を上に上げ、視線を下に向ければ良い。
ボリビア型ケーナ(アチャ式)寸法
(→folklore-ml 01209)
ケーナ
アドリアン 全長 375 吹き口側
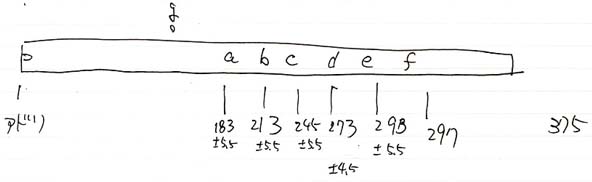 日本の竹を加工する
日本の竹を加工する
1)片方を節にして切る。
節が斜めになっているときは、下の方をカット。
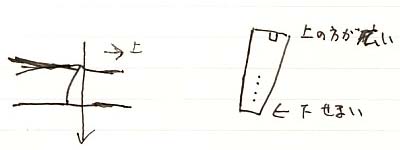 2)底に小さな穴をあけておく。途中で割れにくくなる。
2)底に小さな穴をあけておく。途中で割れにくくなる。
 3)お茶の出がらしを使って良く磨くと美しい色が出るらしい。
4)煮る。竹の蝋をぬく。
3)お茶の出がらしを使って良く磨くと美しい色が出るらしい。
4)煮る。竹の蝋をぬく。
竹が層を成して埋まっているところには、
燃料になるくらいワックスがたまるという。油ぎっているのだ。
・別のやり方として、油(アーモンドオイル、食用油で代用可)を塗って
天火(オーブン)で焼く。200度位(?)
オーブンがないときは、焦げないように注意して、
ガスレンジで時間をかけて焼く。
焼きムラがないように気をつける。
焼いたもの程、鳴りが良くなるらしいが、その分弱くなるので、
ドリルでなく小刀で加工する。
竹は本当は本州になかったそうで、九州から持ち込まれたものだそうだ。
千葉県以南の竹で、立ち枯れているようなものが良いという。