
36・プシピア
プシピア Pusipia ラパス県 ジャーノス・デ・コルケンチャ etc.
アイマラ語で4つの穴の意。踊りより由来した別名モコルル Mokolulu,Mukululu。
大きい方(80cm)をタイカ Tayka(レのケーナの下の穴4つと同じ?)
中 (53cm) マルタ Malta(ラのケーナの下の穴4つと同じ?)径2.8
小 (40cm) ヒスカ Jiska(レのケーナの下の穴4つと同じ?)
4つの穴をふさぐと、大=ド、中=ソ、小=レとなる・・・とカブール氏の本に書いてある。
自分の買ったものは、タイカが1オクターブ低いケーナの(ラのケーナ)下の穴4ヶ
マルタが ミのケナーチョの 下の穴4ヶ
という風だった。
プシピアの音楽は軽快で楽しい(?)もので、メロディーはクシージョ(Khisillo、アイマラ語でサル)
のリズムより生まれた。響線付タイコ(ワンカラ、WanK'ara)と合奏。
ムクルルの踊りに使われる。5〜6月の収穫時期である。
プシピアの小さいものを Mahala Pusippia-niと呼ぶ。(Arte de Folklore de Bol. P48)
表穴3裏1とあった。(少々疑問である)
5月のジャガイモの収穫の音楽などがCD等で日本でも紹介されている。
ピンキージョ類のページに追補。
E.C. P60参
プシピアは他に、歯のない人(老人)用に、リコーダー状の吹き口のものもある。
(→Pinquillo Mukululu)
また、ラパス県オマスーヨ郡ワラタグランデでは、大10,小5本ずつで合奏するという。
歌口は角型で、ケナケナ、チョケーラと同様。長いので指が届きにくい。
演奏は倍音も使うので指穴の数の割に音域は広い(ワカピンキージョ同様)
ワカピンキージョ、プシピア、モセーニョは同系の奏法である。
オスマーヨ郡のものは、9月14日のカルメンの祭りで見られる。乾期のユンガス地方の笛。
似たものとして、ペルー国クスコ県ケロ村のピナピンクルーチャが、
その小型という感じがする。
ピナピンクルーチャとプシピアは、指穴の形か材かその大きさを除けば、
ほぼ同じもののようで、ロリャーノ(クスコ、ラパス、ポトシ)同様、
昔は広く一帯にあった可能性がある。
ケナケナの合奏と共に見られる地域が多い。
参考CD
ボリビアマンタ Winayataqui CD-8 Phusipias de Totorani(ラパス県アロマ郡)
また、プシピアはボリビア、ペルーにあるという。大中小、mama,malta,(ケチュア語)Un~aまたはN~allu
大の長さが69〜67cmと書いてあった。 (M.I. P63)
Mallcu de los Andes にも録音あり
Kollanas B-6 Pusipia
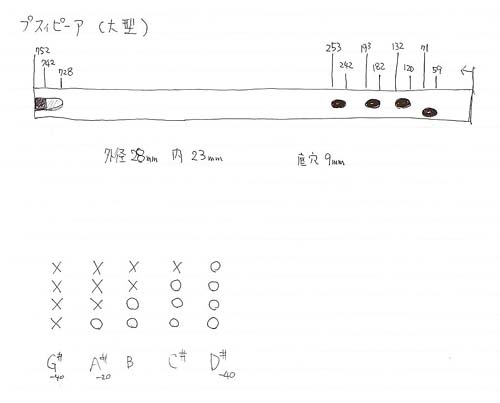
(カブール氏の記載ではこの半音下?)
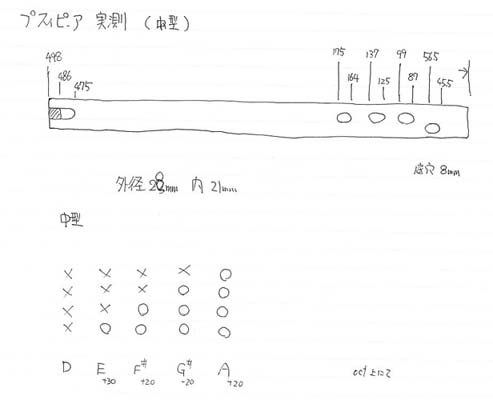
(小型は、ケーナの穴の下4ヶだけと思って良いと思う。)
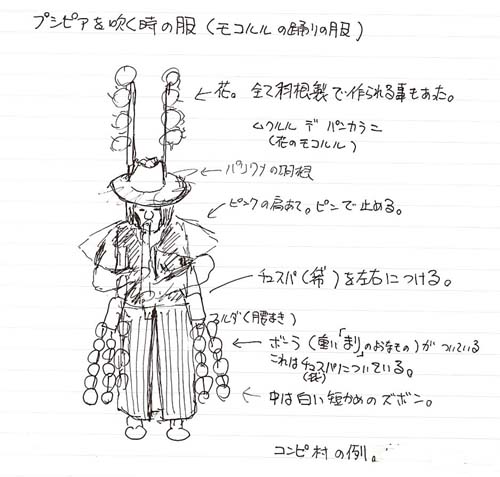
服はワタ村で作られているという。
(サンティアゴ・デ・ワタのカルワニのチョケーラと一部同じ)
道程は、ラパス市からセメリテリオ発で、
Hatalla→Huarina→Huatajata→Chua→Cocani→Compi→
Jamco Amaya→T'ikini→Copacabana(→ペルー国境・・・)
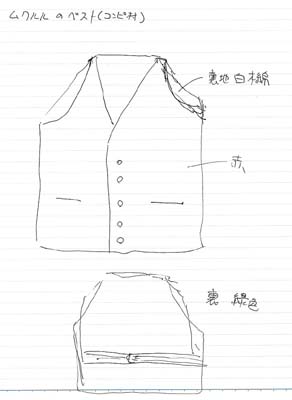
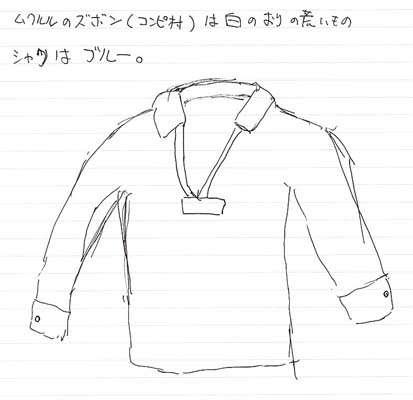

プシピア(ムクルル)や、ケナケナに使われていた。
チョケーラに使っている例は知らない。
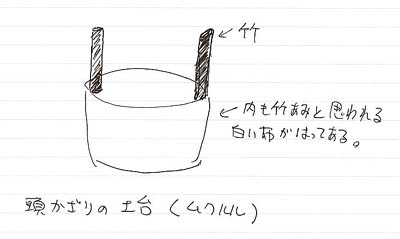 プシピアを実際に吹いてみると
プシピアを実際に吹いてみると
主なメロディーは小さい管が中心となる。
しかし、長い笛の音は小さいんで、
長い笛2:小さい笛1・・・の割合でバランスが取れるのだろう。
ワンカラは、モセーニョに用いたものに音が似ている。
低音パートは平行メロディーでハモっている。
倍音を使うので、最低音域はあまり使わない。
衣装は植物のジャガイモを表しているようだ。
袋は実ったジャガイモの地下茎を表し
ベストの背は葉と同じ緑。
ファルダは毛根。
アバ・パンカラニ(帽子の花の形の飾り)は、
ジャガイモの花を表しているのだろう。
(アバは、今日ではHaba、そらまめ・・・スィートピーを指す)
プシピアの運指(上が吹き口)
× × × × ○ ○
× × × ○ × ○
× × ○ ○ × ×
× ○ ○ ○ × ×
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
4 3 2 1 (3) (2)
という風に、運指を数字で表すと、練習の時にイメージがつかみやすい。ラパス県。
アロマ郡のプシピアを耳でコピーしてみると、こんな運指でカバーできた。
実際は細かいトリルなども入るので、
あくまで参考にしか鳴らない表記法だが、充分使える。

